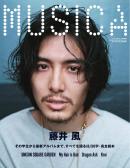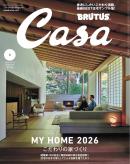できる Google NotebookLM 可能性は無限大!自分専用AIノート活用法
インプレス / 2025年08月27日 / 全207ページ
Googleが提供するAIノートサービス「NotebookLM」が注目されています。GeminiやChatGPTなどがインターネットを含む膨大な情報を学習源とするのに対し、NotebookLMはユーザーが提供した資料だけを情報源とします。このため回答の信頼性が高く、生成AIに不可避のハルシネーションも抑制されています。本書を使ってNotebookLMの力を最大限に引き出し、情報整理や思考の強化にぜひ役立ててください。
目次
- 本書の前提
- まえがき
- 本書の読み方
- 練習用ファイルの使い方
- 目次
- 本書の構成
- 第1章 NotebookLMの基本操作
- L01 NotebookLMをはじめよう<Introduction>
- L02 NotebookLMとは<NotebookLMの概要>
- L03 著作権と情報セキュリティ<NotebookLMの利用規約>
- L04 ソースをアップロードしよう<ノートブックの新規作成>
- L05 画面の構成を確認しよう<画面説明>
- L06 音声概要を作ってみよう<音声概要>
- この章のまとめ NotebookLMを使ってみよう
- 第2章 ソースをもとに情報を生成しよう
- L07 情報を入出力する方法を覚えよう<Introduction>
- L08 [マインドマップ]を作ってみよう<[マインドマップ]>
- L09 ソースの内容を掘り下げよう<回答をソースに追加する>
- L10 学習ガイドを作ろう<学習ガイド>
- L11 資料を要約しよう<ブリーフィング・ドキュメント>
- 本書の前提
- まえがき
- 本書の読み方
- 練習用ファイルの使い方
- 目次
- 本書の構成
- 第1章 NotebookLMの基本操作
- L01 NotebookLMをはじめよう<Introduction>
- L02 NotebookLMとは<NotebookLMの概要>
- L03 著作権と情報セキュリティ<NotebookLMの利用規約>
- L04 ソースをアップロードしよう<ノートブックの新規作成>
- L05 画面の構成を確認しよう<画面説明>
- L06 音声概要を作ってみよう<音声概要>
- この章のまとめ NotebookLMを使ってみよう
- 第2章 ソースをもとに情報を生成しよう
- L07 情報を入出力する方法を覚えよう<Introduction>
- L08 [マインドマップ]を作ってみよう<[マインドマップ]>
- L09 ソースの内容を掘り下げよう<回答をソースに追加する>
- L10 学習ガイドを作ろう<学習ガイド>
- L11 資料を要約しよう<ブリーフィング・ドキュメント>
- L12 FAQを作ろう<よくある質問>
- L13 最新の情報を時系列にまとめよう<タイムライン>
- L14 ソースとして複数の資料を追加しよう<ソースの追加>
- この章のまとめ 基本的な機能の使い方を覚えておこう
- 第3章 ノートブックで情報共有しよう
- L15 チームで情報共有しよう<Introduction>
- L16 閲覧用のノートブックを共有する<ノートブックの共有>
- L17 ユーザーの権限を変更するには<編集権限の付与>
- L18 ユーザーの権限を削除するには<アクセス権を取り消す>
- この章のまとめ チャットボットなどに活用できる
- 第4章 情報をすばやくまとめる
- L19 身の回りの情報をまとめよう<Introduction>
- L20 ビジネスやレポートに役立つ最新の情報を探すには<ソースを探す>
- L21 Webページの情報を短時間で理解するには<Webの情報をまとめる>
- L22 利用規約など煩雑な文書について質問するには<煩雑な文書の要約>
- L23 外国語の契約書の内容を理解するには<複雑な文書の要約>
- L24 アンケート結果から見落としがちな視点を得るには<アンケート回答の考察>
- L25 音声データをもとにセミナーの参加報告書を作るには<セミナー参加報告書>
- L26 Youtubeの動画の内容を短くまとめて報告するには<YouTube動画の要約>
- L27 複数製品のスペックシートから比較表を作るには<比較表の作成>
- L28 補助金などの手続きの流れを把握するには<手続きの確認>
- L29 SNSでの口コミから自社製品の評判を分析する<ユーザー評価の分析>
- L30 資料を「ながら」で理解するための音声概要を作る<音声概要の活用>
- L31 ログファイルから何が起こっているかを読みとく<ログファイルの解読>
- この章のまとめ 情報過多の時代に最適なツール
- 第5章 煩雑な業務を効率化する
- L32 面倒な仕事をNotebookLMにやってもらおう<Introduction>
- L33 複数の修正案を統合して文書に反映するには<修正案の統合>
- L34 文書をひな形のフォーマットに合わせて書き換えるには<文書の形式を変換する>
- L35 会議の録音から議事録を自動的に作るには<議事録の作成>
- L36 社内規約に代わりに回答するしくみを作るには<社内規約の共有>
- L37 タグを使って文書を分類するには<文書の分類>
- この章のまとめ NotebookLMを業務効率化に役立てよう
- 第6章 資料を深堀りして学習に役立てよう
- L38 資料をもっと活用しよう<Introduction>
- L39 自分のレポートを客観的に評価するには<レポートの評価>
- L40 学習の理解度を測るクイズを作るには<オリジナル問題集を作る>
- L41 発表資料から想定される質問と回答を考えるには<想定問答を作成>
- L42 書籍の内容をざっくりと理解するには<書籍の要約>
- L43 仕様書から利用シーンなどの具体例を作成するには<具体例の作成>
- L44 他の人が作ったマクロやプログラムの内容を理解するには<プログラムのレビュー>
- この章のまとめ NotebookLMで知識を深め、発展させよう
- 第7章 雑多なデータをまとめる
- L45 資料と質問の組み合わせで新しい発見を得よう<Introduction>
- L46 資料からたくさんのアイデアを出すには<アイデア出し>
- L47 複数の資料を比較して情報の不備を補うには<資料の比較>
- L48 メモ書きなどの雑多なアイデアを体系的に整理するには<アイデアの整理>
- L49 新人向けのオンボーディング用資料を作るには<オンボーディング用資料>
- L50 みんなの意見をまとめて提案書を作るには<提案書の作成>
- この章のまとめ 面倒な作業を任せよう
- NotebookLMの疑問に答えるQ&A
- 付録 スマートフォンにアプリをインストールするには
- 用語集
- 索引
- スタッフリスト
- 奥付
※このデジタル雑誌には目次に記載されているコンテンツが含まれています。それ以外のコンテンツは、本誌のコンテンツであっても含まれていません のでご注意ください。
※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページがある場合があります。